インボイス制度が建設業者に与える影響は?一人親方が準備すべきポイントを解説
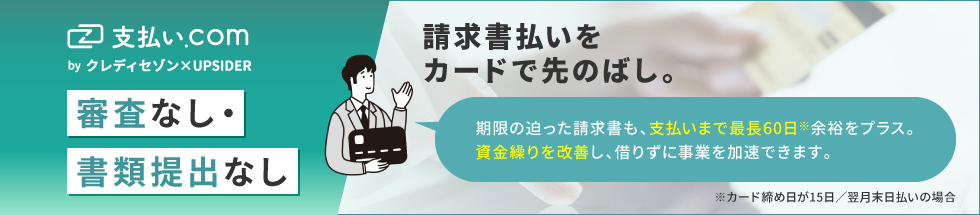
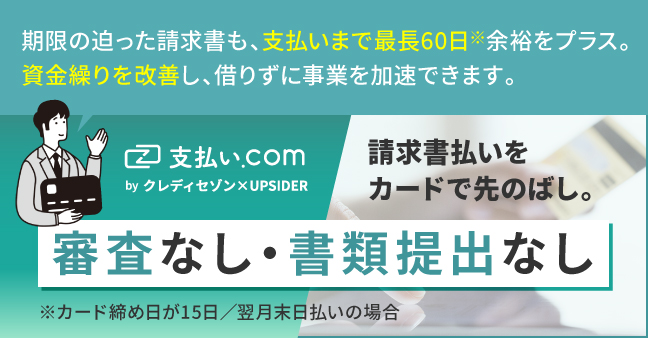
インボイス制度の内容をおさらい
インボイス制度とは?
インボイス制度とは8%と10%、2種類の税率がある取引の中でも正確に納税額を計算できるように仕組化された制度です。インボイス(適格請求書)には発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額を明記したもの、と他にもいくつか規定があり、必要事項が全て明記されていないとインボイスとして仕入税額控除の際に使用することはできません。
またインボイスを発行できるのは税務署に届出をし、インボイス発行事業者として登録を受けた課税事業者のみです。免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者が取引相手の場合は仕入税額控除を受けることができません。(但し2029年まで経過措置あり)
インボイス制度は2023年10月からスタートすることが決まっていて、インボイス発行事業者への登録申請は2021年にすでに始まっています。
インボイス制度の内容については以下の記事でより詳しく解説しています。
【記事】インボイス制度とは? 導入の背景・時期・影響と個人事業主がするべき対応
インボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者のみ
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録申請を行い「適格請求書発行事業者」として認められた課税事業者のみです。免税事業者が発行する請求書はインボイスとして認められないため、取引先が仕入税額控除を受けることができません。
建設業界では、一人親方の多くが免税事業者として事業を行っており、また重層的な下請構造が一般的です。このため、インボイス制度の導入により以下のような影響が考えられます。
● 免税事業者との取引制限
● 取引先からの値下げ要請
● 課税事業者への登録要請
● 多重下請構造における取引関係の見直し
これらの課題に対応するため、免税事業者は課税事業者への移行を含めた事業形態の見直しを検討する必要があります。ただし、2029年までは経過措置が設けられており、段階的な対応が可能です。
建設業界への影響大!インボイス制度で変わること

インボイス制度が始まることで建設業者・一人親方が受ける様々な影響について詳しく解説します。
【建設業者】仕入税額控除を受けられなくなる
取引相手が免税事業者の場合、インボイスが発行されないため仕入税額控除を受けることができません。建設業界は中小企業や一人親方と言われる免税事業者が多く、これまで問題なく受けられていた仕入税額控除が受けられなくなる影響は大きいことが予想されます。
【建設業者】免税事業者へ発注するリスク・コストが発生する
企業側は取引相手が免税事業者だと仕入に係る消費税が控除されず、結果として必要以上の消費税を納めることになりかねません。また免税事業者が発行する請求書はインボイスとは内容が異なるため事務処理の際に別で取り扱う必要があり、その分のコストや手間が増えることが考えられます。このようなデメリットから免税事業者との取引に対して消極的になる企業が増える可能性があります。
【建設業者】会計の処理が複雑になる
インボイス制度スタート後も免税事業者のまま事業を続ける事業者はもちろんいます。その場合会計処理の際は請求書と適格請求書に分けて管理、保管する必要があります。
インボイス制度導入後の消費税の計算方法には”割り戻し計算”と”積上げ計算”の2種類または”併用”があり、事業者は任意で選ぶことが可能です。ただ場合によっては計算方法が適用できない場合や計算方法によって納税額が変わるなど、複雑な会計処理から事務負担の増加が懸念されています。
【一人親方】消費税の納税が求められることになる
インボイスを発行できるインボイス発行事業者になるということは、同時に課税事業者になるということです。免税事業者だった一人親方・大工もインボイス発行事業者になった場合、今後は納税を求められることになります。
【一人親方】適格請求書発行業者になるための手続きが必要
適格請求書を発行するには適格請求書(インボイス)発行事業者に登録し登録番号を取得する必要があります。申請書類に記入し所轄の税務署長に提出することで適格請求書発行事業者への登録が可能です。
【建設業界全体】偽装請負問題の解消
偽装請負問題とは、書類上は個人事業主のような形で業務委託契約としながら社員と同じように働かせることです。企業側は社会保険料などの支払いを免れるため従業員に一人親方として独立を促し、結果として偽装請負と言われる違法な状態での雇用となっている状態が多くありました。インボイス制度の導入により一人親方になることのリスクなどを考えると、そもそも独立を促し一人親方にさせようとすること自体に違和感を覚えやすく、偽装請負問題の解消に繋がると考えられています。
建設業者がインボイス制度に対応するためにすべきこと
建設業者がインボイス制度に適切に対応するためには、取引先との関係を見直し、必要な対策を講じる必要があります。
①取引先が適格請求書発行事業者かを確認
建設業者は、すべての取引先について適格請求書発行事業者の登録状況を確認する必要があります。特に一人親方との取引が多い場合は、取引の継続可否を含めた慎重な判断が求められます。仕入税額控除を受けるためには、取引先が適格請求書発行事業者として登録されている必要があります。
取引先の登録状況確認においては、国税庁が提供する国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトを活用することが効果的です。このサイトでは登録番号から事業者を検索できるため、取引先の登録状況を正確に把握することができます。
確認作業を進めるにあたっては、まず主要取引先から優先的に確認を行い、その後取引金額の大きい順に確認していくことで、効率的に作業を進めることができます。また期限を定めて確認作業を行うことで、取引先との調整に十分な時間を確保することが可能です。
②取引先へ課税事業者への変更を促す
免税事業者である取引先に対して課税事業者への変更を促す場合は、以下の点に注意が必要です。
● 取引条件の一方的な変更を強要しない
● 独占禁止法や下請法に抵触する行為を避ける
● 建設業法で定められた取引適正化の規定を遵守する
取引先との交渉では、情報量や交渉力の格差を考慮し、公正な取引関係を維持することが重要です。特に、一人親方など小規模事業者との取引では、取引条件が一方的に不利にならないよう配慮が必要です。
また2023年10月からの3年間は仕入税額控除の80%が、その後の3年間は50%が認められる経過措置があります。この期間を活用して、取引先との関係を段階的に見直すことで、急激な変更による影響を軽減できます。長期的な事業戦略として、以下の点を考慮することが重要です。
● 取引先の事業規模や取引金額に応じた段階的なアプローチ
● 取引先の経理体制や事務処理能力の把握
● 必要に応じた経理サポートの提供
● デジタル化支援などの業務効率化施策の検討
また、取引先との関係維持のために以下のような施策も検討する価値があります。
・請求書作成の効率化支援
デジタル化に不慣れな取引先向けに、インボイス制度に対応した請求書テンプレートの提供や、クラウド会計ソフトの導入支援を行うことで、円滑な取引関係を維持することができます。
・共同での勉強会開催
税理士を招いてインボイス制度に関する勉強会を開催し、取引先とともに知識を深めることで、制度への理解を促進し、スムーズな移行を実現することができます。
一人親方がインボイス制度に対応するためにすべきこと

課税事業者になるための手続きをおこなう
インボイスを発行できるインボイス発行事業者は対象が課税事業者なので、まずは課税事業者への登録を行います。但しインボイス制度には経過措置期間(2023年10月1日〜2029年9月30日)が設けられています。申請前が免税事業者の場合、この経過措置期間に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書を所轄の税務署長に提出することでインボイス発行事業者と同時に課税事業者の登録も完了します。申請用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁ホームページ
インボイス制度に対応した請求書の書き方を覚える
従来の請求書とは違い適格請求書には必須項目が増えています。1つでも欠けるとインボイスとして使用できないため、事前に内容を理解し書き方を覚えておくといいでしょう。
DXを活用した効率化を進める
建設業界でもデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せており、特に請求書管理や経理業務の効率化が急務となっています。インボイス制度への対応と業務効率化を両立させるには、電子請求書システムの導入が効果的な解決策となります。
電子請求書システムの導入により、業務効率が大幅に改善されます。さらに、郵送費用の削減、人件費の抑制、保管スペースの有効活用など、経費の削減効果も期待できます。
特に注目すべきは、クラウド型の会計ソフトウェアの活用です。これらのツールは以下のような機能を有しています。
● インボイス対応の請求書自動作成
● 取引データの自動仕訳
● 取引先ごとの請求書フォーマット管理
● データのバックアップと安全な保管
● 経理担当者とのリアルタイムな情報共有
システムを導入することで、インボイス制度への対応だけでなく、業務全体の生産性向上にもつながります。
簡易課税制度への変更を検討する
インボイス制度によって複雑化する会計処理による事務負担を軽減するために「簡易課税制度」という制度があります。簡易課税制度では事務負担は軽減しますが、還付金が受けられないなどのデメリットもあるため、制度を受けるにあたって慎重に検討することをおすすめします。簡易課税制度について以下の記事で詳しく解説しています。
【記事】インボイス制度による簡易課税制度への影響をわかりやすく解説
減収を前提とした資金繰りをおこなう
インボイス発行事業者になることで納税の義務が発生します。今まで免税事業者として事業を行っていた時に比べ、減収になる可能性が高いため、減収を想定した資金繰りを行うことが重要です。
具体的な資金繰り改善方法について、下記資料をご参考ください。
shi-harai01.png)
shi-harai01_sp.png)
取引先とインボイス制度導入後の取引について話し合っておく
発注側は免税事業者との取引では仕入税額控除が受けられなくなります。そうしたインボイス制度による影響について一人親方は取引先とよく話し合っておく必要があります。以前まで消費税分も含めた料金だったのに対し、制度導入後は仕入税額控除を受けられないことによる消費税分の値下げを要求されるかもしれません。また、発注側である取引先がインボイス制度導入後は課税事業者との取引に変更しようと考えている場合もあり、その辺りについても事前の話し合いが大切です。
免税事業者が選ぶべき選択肢は課税事業者だけか
インボイス制度導入後、免税事業者は事業形態の選択を迫られています。課税事業者への登録は重要な選択肢の一つとなりますが、慎重な判断が必要です。
課税事業者登録のメリット・デメリット
課税事業者になることの最大のメリットは、適格請求書を発行できることです。これにより取引先が仕入税額控除を受けることができるため、取引関係を維持しやすくなります。
一方で、デメリットとしては消費税の納税義務が発生し、申告書の作成や納付額算出のための数値集計など、事務作業が増加します。また、請求書のフォーマットを適格請求書の要件に合わせて変更する必要があります。
課税事業者登録の検討において、特に建設業界では工事の規模や種類によって影響が異なることに注意が必要です。大規模な公共工事や商業施設の建設では、発注者側が仕入税額控除を重視する傾向が強く、課税事業者であることが事実上の参加要件となるケースもあります。一方、住宅リフォームや小規模な修繕工事などの分野では、最終消費者との取引が中心となるため、課税事業者登録の必要性は比較的低い傾向にあります。
簡易課税制度の適用条件と影響
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択できます。この制度では、実際の仕入額を計算する代わりにみなし仕入率を使用することで、事務負担を軽減できます。ただし、届出書の提出は適用を受けようとする年の前年までに行う必要があります。
適格請求書を発行しない場合のリスク
免税事業者のままでいる場合、適格請求書が発行できないため、以下のリスクが発生します。
● 取引の減少や停止
● 取引金額の減額要請
● 新規取引機会の損失
● 各種支援措置や補助金の利用制限
特に2029年以降は経過措置が終了するため、取引への影響がさらに大きくなることが予想されます。
また、建設業界特有の課題として、工事の受注機会の減少も考えられます。免税事業者のままでは、工事規模や案件の種類によって参入機会が制限される可能性があるでしょう。
一人親方が活用できる支援策や補助金
一人親方が活用できる支援制度には、国や自治体による補助金・助成金制度があります。これらの制度を有効活用することで、事業の継続や発展につながります。
・事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業再編などの事業再構築に取り組む費用の一部を補助する制度です。補助率は2/3〜3/4で、補助額は100万円から1億円となっています。事業計画の作成と認定支援機関による確認が必要です。
・IT導入補助金インボイス枠
インボイス制度対応のためのITツール導入を支援する制度です。会計ソフトや受発注ソフトの導入費用に加え、PCやスキャナーなどのハードウェア購入も補助対象となります。小規模事業者の場合、補助率は最大4/5となります。
・無料相談サービスの活用
東京商工会議所をはじめとする各地の商工会議所では、税理士や社会保険労務士による無料相談窓口を設置しています。インボイス制度への対応や確定申告の方法、各種助成金の申請方法など、専門家に相談することができます。
インボイス制度におけるよくある質問
建設業者のインボイス制度におけるよくある質問を紹介します。
適格請求書の形式や内容は?
適格請求書には、以下の記載事項が必須です。
● 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
● 取引年月日
● 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
● 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率
● 税率ごとに区分した消費税額
● 取引先の事業者名
記載事項に不備がある場合、取引先は仕入税額控除を受けることができなくなり、取引関係に支障をきたす可能性があります。
登録申請はどこで行うのか?
登録申請は、税務署への直接提出またはe-Taxでの電子申請が可能です。e-Taxを利用する場合は、以下の準備が必要です。
● 電子証明書(マイナンバーカード等)
● 利用者識別番号
● 暗証番号
申請時は、事業者情報や公表事項を正確に記入し、必要な添付書類を漏れなく準備することが重要です。
免税事業者が不利になるのはなぜ?
免税事業者は適格請求書を発行できないため、以下の影響を受ける可能性があります。
● 取引先が仕入税額控除を受けられず、取引継続が困難になる
● 取引価格の引き下げを要請される
● 新規取引の機会が減少する
特に建設業界では、多重下請構造により影響が連鎖的に広がる可能性があります。免税事業者は、課税事業者への移行や取引条件の見直しを検討する必要があります。ただし、2029年までは経過措置があり、段階的な対応が可能です。
まとめ
建設業者は中小企業や一人親方など、ほとんどが免税事業者のため、インボイス制度によって影響を受ける事業者が多いことが予想されます。インボイス制度導入後はインボイス発行事業者になることで納税の義務や複雑な経費処理、減収を前提とした資金繰りなど今までとは違った対応が求められる場面が増えます。事前に制度をよく理解し課税事業者になるのか、または免税事業者のままで事業を継続するのか、取引先とよく話し合うことも含めて準備をしっかりしておくことが大切です。

